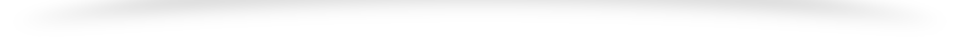こんにちは。ひとりで.comです。
2017年4月1日放送のNEC presents ミライダネは「ICT味覚センサーで食の未来を変える」と題して人工の舌で食の未来を変える”味覚センサー”を特集します。
人間の舌は曖昧?? 同じ味を別の素材で実現する味覚センサー
【目次】
糖質カットのどら焼きは味が変わらない?

全国に80店舗を展開するお菓子メーカー、シャトレーゼ。幅広い品揃えの洋菓子に和菓子も充実している。人気の柏尾山どら焼きは北海道産のあずきを使った贅沢な味わいである。
ここでいま売れに売れているのが糖質カットシリーズのお菓子である。ものによっては、糖質を87%もカットしている。ヘルシーなのは嬉しいが、果たして味はどうなのか…客の反応は「あまり味は変わらない」と評判。
糖質カット商品は、糖尿病を患う人にも好評である。
この糖質カットシリーズの商品開発において活躍しているのが”味覚センサー”である。大幅な糖質カットを実現するには材料の見直しが必要だった。
味覚センサーを使うと、あらゆる食品の味を数値化できるという。そのデータを元に本物のどら焼きの味を全く別の食材で実現したというのである。
だしのベストなブレンドを実現したマルトモ
この味覚センサー、マルトモのかつおぶしでも活用されていた。マルトモは愛媛県に本社を置く創業100年を迎えるかつお節の老舗メーカーである。
マルトモでは、よりおいしいだしを開発するために味覚センサーを用いて、様々なブレンドを実験。何度もそのブレンドを変更し、データでどのブレンドが一番いいポジションにいるか検証し最高の配合を選び、新商品を開発した。
味を数値化できる”味覚センサー”は様々な食品で活用され、現在その販売数は400を超えた。
5種類の味覚を数値化:味覚センサー

この味覚センサーを開発しているのが、神奈川県厚木市に本社を置く、電子計測器メーカーのアンリツの敷地に間借りしている株式会社インテリジェントセンサーテクノロジーである。略してインセント。
味覚センサーはうま味、塩味、酸味、苦味、甘味の5種類の味覚をで見極め、コンピュータが解析し、目に見える形で数値化することを可能にしている。
例えば、コーンクリームスープ。味を数値化して、それを別の食材で作ることができる。なんと、牛乳とたくあんを混ぜると、コーンクリームスープと同じ味ができるというのである。さらに、コーヒー牛乳は、牛乳と砂糖と麦茶を混ぜることによって同じ味が実現できる。このように味を数値化することによって、別の食材を使って同じ味を実現できるのである。
地方の魅力発信にも味覚センサーがひと役
島根県にある森田醤油店は国産の原料に拘って、昔ながらの製法で醤油を作り続けている醤油メーカーである。この森田醤油店では、少し違った形で味覚センサーが活用されていた。
それは醤油の特徴を味覚センサーで数値化し、大手メーカーの醤油との違いを図式化し、営業ツールとして役立てているのである。
味の違いは、言葉だけで伝えるのはとても難しく、他社との比較も客観的に表現するのが難しい。そこで、味覚センサーで出た数値を並列に並べることによって、違いを可視化できるという点を活用したのである。
この仕組みを作ったのが、島根県商工会連合会である。地元の60種類の商品を味覚センサーで分析し、わかりやすく冊子化し、営業活動などに役立てているのである。
味覚センサーが地方の魅力発信に一役買っていた。
味覚センサーの生みの親:九州大学・都甲潔教授
そんな味覚センサーの生みの親が九州大学・都甲潔教授である。
科学者の間では知らない人はいないというほどの有名人でこれまで数々の賞を受賞してきた。そんな都甲教授の最大の功績が、これまで実現不可能と言われてきた味を数値で測る仕組みを世界で初めて実用化したことである。
味覚センサーを開発しようと思ったのは、都甲教授が生物物理学の研究をしていた30年ほど前。そのきっかけは、奥さんが作ってくれた特製のハンバーグだった。
にんじん嫌いの都甲教授に、奥さんがにんじんをすりおろしたハンバーグを作り、それをおいしいと食べた事にある。
なんて人間の味覚は曖昧なものなのだ…より味覚センサーを作ろう
と思ったと言う。ここから味の数値化という膨大な挑戦が始まった。
そもそも人間の舌には生体膜というものがあり、その生体膜に食品が触れると電圧が起こり、味神経を伝わって、それが脳に信号として送られる。そして脳がその味を認識するという仕組みになっている。
従って、その生体膜を人工的に作り出すことができれば味を認識することができるのではないかと考え、人工的な生体膜の開発を行った。
そんな都甲教授は富士食品工業という調味料メーカーで難題の解決に挑戦していた。このメーカーではいま流行りの減塩商品の見える化に挑戦していた。しかし、現在の味覚センサーでは、塩味を感じさせる物質を計測することができないため、新たな膜の開発が必要なのである。